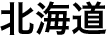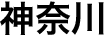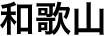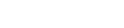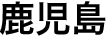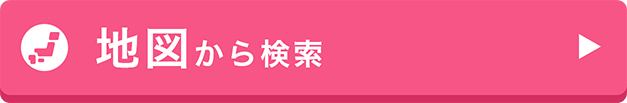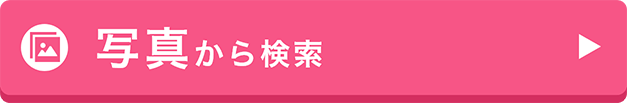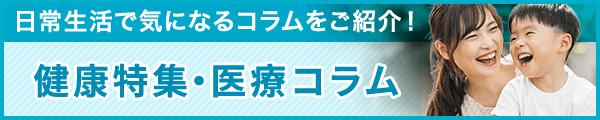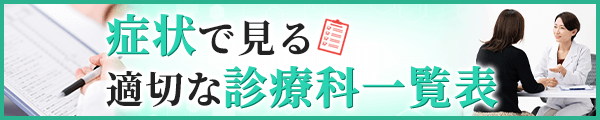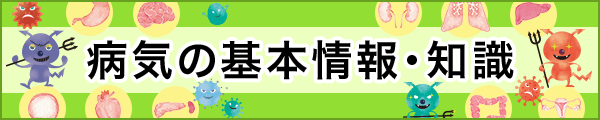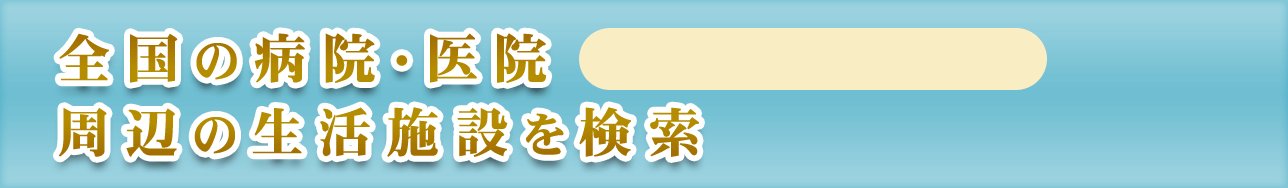 心臓血管外科
心臓血管外科
心臓血管外科病院をお探しの方は、ドクターマップにお任せください!施設情報サイト「ドクターマップ」では、日本全国の心臓血管外科に対応した病院の情報をまとめました。検索方法もカンタン!都道府県名から地域を選んで、お目当ての心臓血管外科のある病院が見つかります!
心臓血管外科とは
心臓血管外科とは、心臓や大動脈を主な対象とし、先天性心疾患、心臓弁膜症(しんぞうべんまくしょう)、冠動脈疾患(かんどうみゃくしっかん)などの疾患に対して外科的治療を行う医学領域です。
主な手術は、大動脈瘤や大動脈解離に対する人工血管置換術、心臓弁膜の狭窄(きょうさく)や閉鎖不全症に対する弁形成術や弁置換術など。また、狭心症(きょうしんしょう)や心筋梗塞(しんきんこうそく)の治療には、冠動脈バイパス術が用いられます。
手術時には人工心肺装置を使用。体外循環を行い、心臓を停止させた状態で内部修復を施行します。平均20年以上に及ぶ長期予後を考慮した、術後管理体制の確立も大切な課題です。さらに、抗凝固療法(こうぎょうこりょうほう)による血栓塞栓症(けっせんそくせんしょう)の予防も欠かせません。常に新しい医療を取り入れ改良されるのが、心臓血管外科の特徴であると言えます。
目次
心臓血管外科で受けられる診療
「心臓血管外科」は、心臓や血管の疾患を外科手術で治療します。
心筋梗塞や狭心症などの心臓疾患、大動脈瘤や大動脈解離などの大動脈疾患、静脈血栓症(エコノミークラス症候群)や静脈瘤などの末梢血管疾患の大きく3つの疾患を扱います。
心臓血管外科での治療内容としては、狭心症や心筋梗塞を対象とした冠動脈バイパス手術、弁膜症を対象とした人工弁置換術、主に僧帽弁閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症を対象とした弁形成術、先天性の心房中隔欠損、心室中隔欠損を対象とした心房中隔欠損閉鎖術・心室中隔欠損閉鎖術、大動脈瘤を切除し人工血管で置き換える大動脈瘤手術、閉塞性動脈硬化症に対するバイパス手術などがあります。
心臓血管外科で診療できる病気一覧
心臓血管外科で診療できる主な病気をご紹介します。
エコノミークラス症候群(えこのみーくらすしょうこうぐん)
特徴
エコノミークラス症候群とは、乗り物の中で長時間同じ姿勢を保ったままでいることにより足の血行障害に伴って起こる種々の障害のことで、略称はエコノミー症候群。発症は飛行機、長距離バス、電車などを始め、狭い空間に座る映画館や劇場、災害の被害時の避難所や車の中などです。
エコノミークラス症候群は細かく分類すると、足の深い場所にある深部静脈に血栓ができる深部静脈血栓症と、その血栓が肺まで移動して肺の動脈に詰まる肺血栓塞栓症の2種類があります。
症状
軽度のエコノミークラス症候群あるいは深部静脈血栓症では、足のしびれやこわばり、立ち上がったときによろける、上手く歩けないなどがありますが、血栓ができると片方の足の腫れや足の痛みを感じます。
肺血栓塞栓症を起こすと、血栓が肺の血管をふさいてしまうために、息切れ、息苦しさ、冷や汗、動悸などの症状が現れ、意識不明から死亡することもあり侮れません。症状は狭い場所にいるときに起きることが多いですが、その後、数日経ってから起きることもあり注意が必要です。
治療法
エコノミークラス症候群には特別な治療法はなく、肺血栓塞栓症になった場合には迅速な対応が必要。乗り物内でのエコノミークラス症候群の予防には、多少の動きが可能であれば手足を動かすことや、ふくらはぎをもむことで血液の流れを良くすることができます。
また、足の血管を締め付けない、ゆったりとした服装や十分な水分の補給なども効果的です。また、災害時に車中泊をすることになったときには、足を高く上げて寝ることも血流の停滞を防げます。
エプスタイン病(えぷすたいんびょう)
特徴
エプスタイン病とは、先天的に三尖弁が右心室内にずれ落ちていて心臓の三尖弁の締りが悪く、強い血液の逆流が生じている難病指定217の心臓病のこと。通常、三尖弁の弁膜症は主に僧帽弁や大動脈弁の異常に伴って発症するのですが、エプスタイン病の場合、三尖弁自体の病変で発症します。
エプスタイン病は遺伝する傾向が一部認められていますが、はっきりとした発症の仕組みは分かりません。確定診断は、胸部X線透視での特徴的な心肥大と、心エコーでの三尖弁逆流から可能です。
症状
エプスタイン病の症状は、全くの無症状の患者から重い症状を示す患者まで多様です。年齢が低いときに見つかるほど重症で、誕生後早期にチアノーゼや呼吸音から発見されますが、初めのうちはほとんど無症状で、学童期になってから心雑音や不整脈で見つかる場合も少なくありません。
成人に達したあとは、年齢が上がるにつれて、不整脈、動悸、息切れ、むくみなどの症状が出やすくなります。頻脈を伴う不整脈が改善しない場合には、入院加療も必要です。
治療法
エプスタイン病の治療は、新生児、幼児期に発症した場合には手術が、その後は経過観察を行いながら、症状が悪化した場合に対症療法が適用されます。
例えば、不整脈には不整脈治療薬や、太ももの血管から挿入したカテーテル先端から高周波電流を心臓に流して治療する高周波カテーテルアブレーション、心不全状態になった場合には、強心剤、利尿剤、降圧剤投与などです。
それでも症状が改善しない場合には、手術の適用で、弁を新しい物に置き換える弁置換術、または弁を修復する弁形成術をしなくてはなりません。
狭心症(きょうしんしょう)
特徴
狭心症とは、心臓に栄養を運ぶ肝動脈の内壁が狭くなって十分な血液が流れなくなった状態で、狭心症特有の胸の痛みが出ることで気付きます。
原因としては、動脈硬化による血管内のプラークの形成や血管内壁の石灰化による狭窄が主なものです。その他に、大動脈弁の弁膜症に伴う発症や、子供の川崎病の後遺症としての発症例もあります。
狭心症は、動いているときに発作が起きる労作性狭心症と安静時に発作が起きる安静時狭心症、不安定狭心症の3種類です。
症状
狭心症発作の症状としては胸の痛みですが、痛みの個所は心臓に近い部分に止まらず、胸の中央、みぞおち、肩、首、腕、顎、歯、目の後ろ側など上半身の広い範囲に渡り、痛みを感じる部位が時間とともに移動するのが特徴です。
また、食べた物が喉に詰まったときに感じる締め付けられるような痛み、押し付けられるような痛みを感じます。
このような症状が30分続き、その後は全く嘘のように収まってしまいますが、発作は突発的に起き、しばらくしてから再び同じような症状が現れるため注意しましょう。痛みが時間とともに移動するだけでなく、最初から肩や胃の痛みのように出ている場合もあり、放散痛と言われています。
治療法
狭心症の治療は、薬物療法または手術、及び生活習慣の改善が中心です。薬物療法には、血管を拡張させて血流を改善させる薬剤や、心筋梗塞予防用の血栓防止薬が使われます。狭心症の発作時の対症療法としては、ニトログリセリン(舌下錠あるいはスプレー)が有効。
狭くなった血管をもとに戻すには、心臓カテーテルや冠動脈バイパス手術を行わなくてはなりません。その他、減塩食、低カロリー食、適度の運動、十分な睡眠、禁煙、アルコールを控えるなどの生活習慣の改善が狭心症予防に効果的です。
心筋梗塞(しんきんこうそく)
特徴
心筋梗塞とは、心臓を動かす血管である冠動脈が動脈硬化に伴い、血管内の内側が狭くなって詰まってしまい、結果として心筋細胞が壊死する病気です。そのため心臓の機能が著しく低下し、死亡してしまうこともあります。心筋梗塞は、急に起こることがほとんどです。
原因は、ずばり動脈硬化。やわらかく、しなやかな血管が生活習慣の乱れによって固く詰まりやすくなってしまうのです。動脈硬化は、不摂生な食事、運動不足、喫煙、飲酒、過度なストレスなどによって、大きく影響されることが分かっています。
例えば、動物性脂肪の多い高カロリー食は、過酸化脂質を増加させ、それらが血管の壁に付着して詰まらせたり、破れたりする原因になります。動脈硬化は年齢とともに進行するため、一種の老化とも言えますが、若い頃からの生活習慣の見直しで予防することが大切です。
症状
急性心筋梗塞の主な症状は、胸部の激痛、締め付け感、圧迫感が30分以上継続することです。呼吸困難、吐き気、冷や汗を伴う場合は、重症であることが多いとされています。
高齢者では、このような特徴的な胸部の痛みではなく、吐き気や息切れなどの消化器症状で発症することも。また、高齢者や糖尿病を患っている場合は、無痛性のこともあります。
治療法
心筋梗塞の治療では、すぐに救急車を呼ぶことが救命に大きく貢献します。心筋梗塞で意識を失ってしまうような場合は、周囲の人がAED(自動体外式除細動器)を使用することによって救命率が上昇。AEDとは、体外から衝撃を与えて脈の乱れを治す装置で、近年では駅構内やコンビニの傍などにも備え付けられています。
その後、呼吸をしていないようであれば、すぐに心臓マッサージを行うことが必要です。また救急車内では、AEDの他に酸素吸入などの処置をします。
病院到着後に、カテーテルを使った「風船療法」またはステントによる治療法が行われることが一般的。どちらも、詰まった血管を広げることが目的です。場合によっては、冠動脈バイパス術という外科的手術が行われることもあります。
三尖弁膜症(さんせんべんまくしょう)
特徴
三尖弁弁膜症とは、右心房と右心室の間にあり、静脈血がこの弁を通して右心室に流入する三尖弁がきちんと締まらなくなり、その部分で血液が逆流する病気です。三尖弁自体に障害がある場合と、三尖弁自体は正常でも他の病気のせいで発症する場合があります。
他の病気の場合、僧帽弁弁膜症や大動脈弁弁膜症に伴って右心室が拡大して三尖弁が引き延ばされて逆流が起きることが多い他、肺動脈高血圧症や感染性心内膜炎などでも発症することがある複雑な病気です。
症状
三尖弁膜症は初期には症状が現れませんが、僧帽弁弁膜症が進行して起きる場合には三尖弁の逆流が重症化して顔面や下肢にむくみが現れ、全身の倦怠感も加わります。
また、不整脈である心房細動が起きやすくなり肺動脈高血圧を起こすため、息切れ、動悸、めまい、失神、咳などが症状として現れ、その後、心不全に移行して突然死にもつながるため放置はできません。
正確な病状の診断には心エコー検査を行って、心臓の動きや弁膜からの血液漏れの状態を確認することが有効です。
治療法
三尖弁膜症の治療は、軽度の場合には特に必要はありませんが、心不全状態になった場合には利尿剤の投与が行われます。さらに重症化して、利尿剤の効果がなくなった場合には手術適用です。
弁の周囲が拡大して血液の逆流が進んできた中等度以上の症例では、人工弁への置換手術あるいは弁形成術が必要。弁置換手術は機械弁か生体弁が選択され、弁形成術は弁の周りを縫って漏れを防ぐ方法と人工のリングを弁の周りに縫い付けて緩くなった部分にふたをする方法です。
血栓を作りにくい点では生体弁が優れているのですが、耐久性が15年程度と短いというデメリットもあります。
ただ、手術は僧帽弁の手術と同時期にする場合が多く、リングで弁形成をすることが多いです。
大血管転位症(だいけっかんてんいしょう)
特徴
大血管転位症とは、完全大動脈転位症とも言う先天性心疾患のひとつで、通常とは逆に右心室から大動脈が、左心室から肺動脈が出るという血管の配置になっている難病(指定難病209)です。
この病気には、心室中隔欠損や肺動脈狭窄という別の先天的奇形を伴うことがあり、これらの奇形のないものをI型、心室中隔欠損を伴うものをII型、心室中隔欠損と肺動脈狭窄を伴うものをIII型と区分しています。
全く治療をしなければ、数ヵ月以内に半数が死亡。診断がつき次第、手術のできる病院への転院が進められます。
症状
大血管転位症の症状は、新生児に特徴的なチアノーゼ(血液中の酸素不足により、皮膚や粘膜が紫色に変色する)が認められること。酸素を吸入してもチアノーゼは改善せず、強い呼吸困難はないのが特徴。生後すぐに強度のチアノーゼが現れる場合には、身体全体の細胞や組織に酸素が行き渡らずに、代謝性アシドーシスと呼ばれる危険な状態なることもあるので細心の注意が必要です。
心エコー検査を行って、大血管の位置を確認することで確定診断ができます。心音や局部レントゲン写真による心臓の大きさの検査では異常所見が見つかることもありますが、確定診断はできません。
治療法
大血管転位症は、そのまま放置すると死亡率が高く、基本的には手術適用です。位置が逆になっている動脈を入れ替えて正常な位置に戻す大手術(ジャンテ手術)で、対象が幼児のため何度かに分けて行われることも少なくありません。
この手術の成功率は高いものですが、その後、不整脈、肺動脈狭窄、大動脈弁や三尖弁弁膜症の発症などの後遺症が出てくる可能性があり、手術後の長年に亘る経過観察が必要となります。
一方、チアノーゼへの対応としては血管を広げる薬を用いて、カテーテルでの治療も可能ですが、これは根本的治療ではありません。
肺動脈狭窄症(はいどうみゃくきょうさくしょう)
特徴
肺動脈狭窄症とは、心臓の右心室から肺へ血液を送る肺動脈に生まれつき狭い部分がある病気です。血液の流れが悪くなるために、血液を送り出す右心室に大きな負担がかかり、心臓の筋肉が厚く大きくなることが特徴。
肺動脈狭窄症は、先天性の心疾患の1割近くを占める病気で、肺動脈狭窄症を含む先天的な心臓の病気の多くは、いくつかの遺伝子の異常や胎内の環境が影響しあって発生すると考えられています。なお、妊娠中に妊婦が風疹にかかることで生じる先天性風疹症候群の症状のひとつとして、肺動脈狭窄症が現れることも少なくありません。
症状
軽症の肺動脈狭窄症は、自覚症状がないことも少なくありません。中等症であっても幼い頃はちょっと疲れやすいという程度ですが、年齢とともに動悸や息切れが現れることが多いです。
重症になると、生まれた直後に全身の酸素が足りなくてチアノーゼと呼ばれる症状を起こす場合もあり、すぐに手術が必要となることもあります。
また、十分にミルクを飲むことができなかったり、体重が増えにくかったり、呼吸回数が多いといった症状が現れることも多く、最も重症なケースでは突然死にもなりかねません。
治療法
軽症の肺動脈狭窄症は治療の必要がないことも多いですが、中等症から重症の場合は血管の狭い部分を広げる治療が必要です。血管を広げる治療には、カテーテル治療と手術があります。カテーテル治療とは、血管から細い管を挿入して心臓まで進めて治療を行う方法です。
手術を急ぐ必要がない場合、小児期にはカテーテル治療を行い、成人してから手術を行うこともありますが、カテーテル治療で対応できない場合には、開胸手術を行わなくてはなりません。なお、重症度が非常に高い場合には出生後すぐに手術を行うこともあります。
外科の基本情報・知識
心臓血管外科のブログ情報
以下の都道府県をクリックして心臓血管外科を検索してください。
「心臓血管外科」から病院名を入力して探す
心臓血管外科の関連情報・生活便利情報
関連情報リンク集
病院・医院に関連する省庁サイトです。
法律や制度の確認、統計データの取得など、情報収集にご利用ください。
心臓血管外科 関連学会一覧
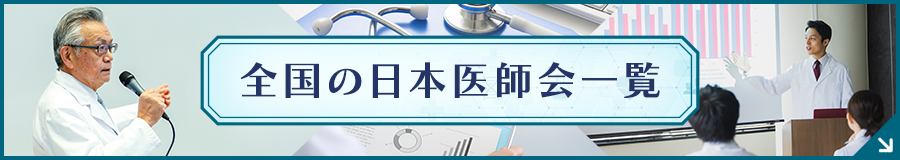
介します。

投稿をお待ちしております。
ホームメイト・リサーチに
口コミ/写真/動画を投稿しよう!
「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。
Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん
- ゲストさんの投稿数
-
今月の投稿数 ―施設
- 累計投稿数
-
詳細情報
―件
口コミ
―件
写真
―枚
動画
―本