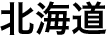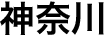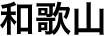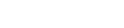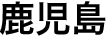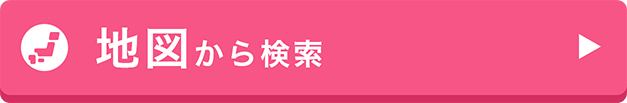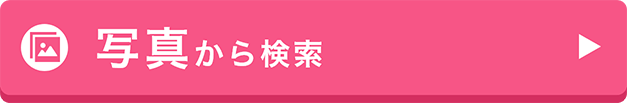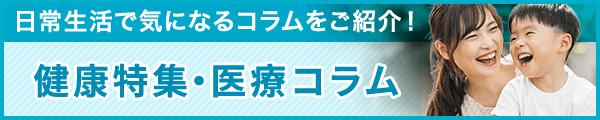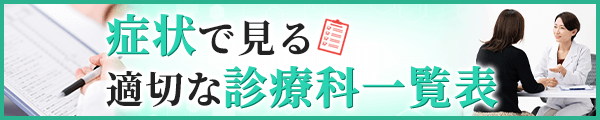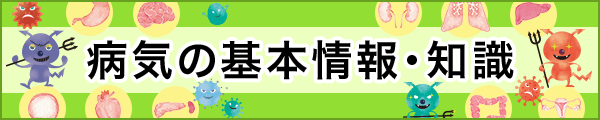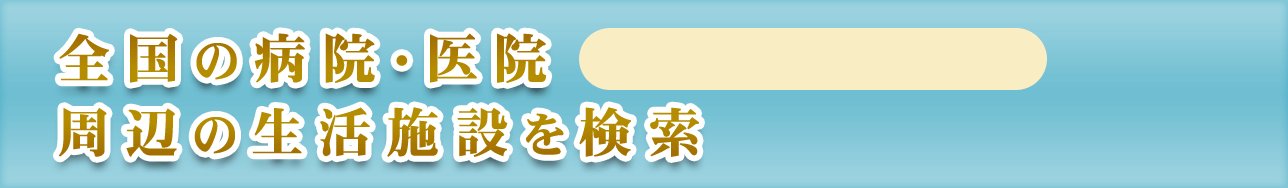 外科
外科
外科病院をお探しの方は、ドクターマップにお任せください!施設情報サイト「ドクターマップ」では、日本全国の外科に対応した病院の情報をまとめました。検索方法もカンタン!都道府県名から地域を選んで、お目当ての外科のある病院が見つかります!
外科とは
外科とは、手術による治療を実践する臨床医学の一領域。代表的な外科領域として挙げられるのは、一般外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、小児外科などです。
外科医は、スカルペルやメスなどの器具を用いて、身体の切開・摘出・縫合などの技術によって病気の治療を行い、手術手技の熟練だけでなく、術前・術後の総合的医療判断が要求されます。
外科手術では麻酔科医との連携も欠かせず、ときに内科や放射線科など関連診療科との合同カンファレンスで治療方針を決定するケースも少なくありません。近年では、腹腔鏡・胸腔鏡下手術など低侵襲治療(痛みや出血などを少なくする治療)も多用されています。
目次
外科で受けられる診療
外科で診療できる病気一覧
外科で診療できる主な病気をご紹介します。
胆石症(たんせきしょう)
特徴
胆石症とは胆肝系に石ができる病気で、石が形成された場所により主に胆嚢結石、総胆管結石、肝内結石の3種類に分けられます。このうち、胆嚢結石が最も多く70~80%程度。石の成分は、コレステロールやビリルビンカルシウム、あるいはビリルビンカルシウムに鉱物の混じったものなどです。
世界的に見ると、加齢白人、肥満、女性、多産、脂質異常症などがリスク要因として挙げられていますが、日本人については男性患者の方がやや多くなっています。
症状
胆石症の症状として、一般的には胆嚢がある下腹部の痛みや心臓から肋骨付近にかけての痛みが特徴的ですが、無症状の場合も多くあります。また、発熱、嘔吐、黄疸などの症状が出ることも稀ではありません。
無症状の場合には、そのまま放置しても症状が出ることはあまりありませんが、急性胆嚢炎などを発症した場合には、熱と痛みなどの症状が現れることが多いです。
カルシウム分の多い石はX線透視で確認が可能で、また、腹部エコー検査も結石の確認に有効な方法になります。
治療法
症状のない胆石は、経過観察の対象です。胆嚢炎などを併発して症状が現れた場合には手術が行われますが、その場合、開腹あるいは腹腔鏡下での胆嚢摘出となります。
手術以外の、胆石症の治療法のひとつは、胆石を特殊な薬剤を用いて溶かして、排出させる溶解法。この方法は、特にコレステロール胆石に対して、有効であることが実証済みです。
また、身体の外から衝撃波を当てて石を砕く対外衝撃波結石破砕療法(ESWL)も高い効果のある方法と言えます。
大腸ポリープ(だいちょうぽりーぷ)
特徴
大腸ポリープとは、大腸の粘膜の一部が盛り上がり、いぼ状になったもので、直腸や結腸に生じるポリープの総称です。
大きく「腫瘍」と「それ以外のポリープ」の2つに分けられます。大部分のポリープは「腺腫」と言う良性の腫瘍ですが、1㎝以上になると部分的に小さな癌が発生していることが多くなり、長期間放置していると進行癌になる可能性が高くなります。
その他に、炎症性や過形成によるポリープもあります。炎症性のものは、腸に強い炎症を起こす病気にかかったあとにできます。いずれも良性で放置しても、癌化することはほぼありません。
症状
大腸ポリープは、大腸や直腸の内壁に、いぼ状やきのこ状に隆起したものができることで、ほとんどの場合で自覚症状がありません。小さいポリープであれば無症状であることも多いため、早期で見つけるためには癌検診を受けることが必要。
ポリープが大きくなってくると排便時に擦れて出血したり、血液の混ざった便が出たり、便が出にくくなったり、腹痛や下痢などの症状が出ます。
成長したポリープが肛門から飛び出したり、肛門の近くで大腸を塞いだりすることも稀に起こり得る症状です。
治療法
大腸ポリープは、内視鏡的切除を行うことが基本的。内視鏡的切除には、ポリペクトミー(ポリープの茎にワイヤーをかけて切除)、内視鏡的粘膜切除術[EMR](茎がない平坦なポリープに用いられる)、内視鏡的粘膜下層剥離術[ESD](範囲が広い病変に対し電気メスで粘膜下層を剥離して切除)の3つ方法があります。
すべての大腸ポリープが内視鏡の適応となる訳ではなく、6mm以上の良性ポリープと、リンパ節に転移している可能性がほとんどなく、内視鏡で一括切除できる癌のみが内視鏡適応となるポリープとなります。
膵嚢胞(すいのうほう)
特徴
膵嚢胞とは、膵臓の中や周辺にできる、種々の大きさの液体を入れた袋状の組織で、袋の中身が細胞でできている真正嚢胞と、膵液で満たされている仮性嚢胞に分けられます。前者は、先天的にできた嚢胞や腫瘍性嚢胞であり、後者は、膵炎の炎症に伴って現れる嚢胞や、けがによってできる非腫瘍性嚢胞です。
腫瘍性嚢胞のうち、粘液性嚢胞腫瘍(MCN)や膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)は膵臓癌になるリスクがあり、慎重な対応をしなければなりません。発生原因は、慢性膵炎、肥満、喫煙、アルコール摂取などになります。
症状
膵嚢胞の中の仮性嚢胞の症状で、一般的にみられるのは腹痛で、腹部を手で押すと痛く、食後に痛みが出るのが特徴です。IPMNでもほとんどの場合は無症状ですが、癌化した場合には腹痛、嘔吐、体重減少が認められ、糖尿病のコントロール中に数値が悪化した場合にも、癌化の可能性への注意が欠かせません。
さらに嚢胞が大きくなると、その形成部位周辺の臓器を圧迫することから、出血や感染による発熱、腹痛などが起こることもあります。膵嚢胞の検査には、色々な方法がありますが、特に超音波内視鏡検査が、胃などから患部の近くを詳細に観察できる点で優れた方法です。
治療法
膵嚢胞の中の仮性嚢胞は、良性で自然に縮小することもあるため、治療の基本は経過観察で、その間に絶食と点滴などの内科的な治療が効果的です。縮小が認められない場合には、袋のできている部分を他の臓器と繋ぎ、嚢胞内部の液体を体外へ排出させるような手術が行われます。
腫瘍性嚢胞は、癌化のリスクがあるため、形成部位や嚢胞の大きさを考慮しながらの開腹あるいは腹腔鏡での手術適用となりますが、そのすべてで膵全摘出が必要になる訳ではありません。
肝硬変(かんこうへん)
特徴
肝硬変とは、ウイルス性肝炎やアルコール性肝炎などにより、繊維(コラーゲン)が異常に増加・凝縮して肝機能の低下を引き起こす病気です。「肝細胞の繊維化」とも呼ばれています。
繊維(コラーゲン)とはタンパク質の一種であり、肝硬変で特徴的なのは、繊維が増加し一塊に凝縮されるため肝臓全体が岩のように固くなることで、肝臓自体も縮小。肝機能の著しい低下で黄疸や浮腫(むくみ)、腹水、さらに重症例では肝性脳症などが見られることが特徴です。
症状
肝硬変で特徴的な症状は、黄疸や浮腫。黄疸とは白目の部分や身体の皮膚が黄色くなることで、比較的気付きやすく、肝硬変発見の手掛かりとなることが最も多い症状です。
その他、腹水も比較的高頻度で見られ、お腹に水が溜まり下腹部が膨満したり、重症例では腹部全体が大きく膨れたりします。酷くなると、肝性脳症などが引き起こされることも少なくありません。
また、肝臓の繊維化に伴い血管が圧迫されることで、食道や胃などに静脈瘤ができ、血液中の血小板が減少することも顕著です。特筆すべきは、肝硬変では症状の全くない時期(「代償期」と呼ぶ)が存在する点。そのため、病気に気づかず重症化してしまうことが多くあります。
治療法
肝硬変に直接有効な薬剤は存在しません。そのため、肝硬変になってしまった場合には、予後を良好にする(症状を悪化させない)ことが最優先事項となります。
低栄養の状態が肝硬変を悪化させることが認められているため、栄養療法(食事内容・摂取量の見直し)や適度な運動・エクササイズなどを行うことが重要です。
また、肝炎ウイルスの中でも、C型肝炎ウイルスが原因の肝硬変では、インターフェロンの単独または併用療法が奏功することがあり、保険適用も可能。アルコール性肝炎が原因の場合に前提となるのはアルコール摂取の制限で、その他、薬物療法では分岐鎖アミノ酸を補うと良いことが多数報告されています。
乳腺線維腺腫(にゅうせんせんいせんしゅ)
特徴
乳腺線維腺腫とは、乳房にしこり(腫瘍)ができる病気のこと。原因は不明であることが多く、また腫瘍も良性であることが多いです。20~35歳の女性に多くみられます。ただ、悪性の腫瘍(癌)と見分けることが難しいため、自己判断せずに婦人科を受診するようにしましょう。
癌化することは、0.02%とごく稀な病気です。発症するのが思春期に多いことから、ホルモンに関係していると言われますが、その原因は解明されていません。
症状
乳腺線維腺腫種の症状は、乳房に硬いしこりができます。しこりの大きさは、1~2cm程度の物から、大きい物ではゴルフボール大の物まで。個数も、単体だったり複数だったりと人によって様々です。コリコリしたようなしこりですが痛みを伴わず、周囲とくっついていないためよく動きます。
妊娠により大きくなったり、閉経で小さくなったりすることもあるのが特徴。癌の場合、はじめは動いても進行するにつれて根を張り、動かなくなることもあるため注意しましょう。
治療法
乳腺線維腺腫は、しこりが小さければ特に治療などはせずに、定期的な検診で経過観察していきます。ただ、急にしこりが大きくなった、痛みが出たなどした場合は、悪性であるかどうかを調べるための検査が必要。検査方法はマンモグラフィやエコー検査を用いて、穿刺(せんし)で細胞を取り、顕微鏡で組織などをみる方法です。
しこりは、稀に大きくなる場合があります。大きくなれば葉状線種の可能性もあり、切開手術が必要となりかねません。
十二指腸潰瘍(じゅうにしちょうかいよう)
特徴
十二指腸潰瘍とは、何らかの理由で十二指腸の壁を覆う粘膜に障害が生じ、十二指腸の壁が深くえぐれてしまう病気です。症状が進むと、十二指腸の壁に穴があいてしまうこともあります。
発症にはピロリ菌の関与が指摘されており、胃酸の分泌量が多い人に良く見られることが特徴。腰痛や関節痛に使われる一部の痛み止めや、血液をサラサラにする働きを持つアスピリンなどの長期間服用が原因で発症することもある病気です。
その他、ストレス、飲酒、喫煙など生活習慣の乱れも発症に関与すると考えられているので気を付けましょう。
症状
十二指腸潰瘍になると、上腹部や背中に痛みが出ることがあります。腹部や背中の痛みは空腹時や夜間に強くなり、食事を摂ると一時的に治まることが多いです。食欲不振や胃もたれ、胸焼けといった症状が現れることも少なくありません。
傷口から出血がある場合には吐血したり、不自然なくらい真っ黒な便が出たりすることもあります。出血量が多い場合に、症状として出てくるのは貧血です。一方で全く症状がなく、健康診断などで偶然見つかるケースも珍しくありません。
治療法
十二指腸潰瘍の治療にあたっては、まずピロリ菌感染の有無を調べることが必要です。ピロリ菌陽性の場合は除菌治療を行いますが、除菌に成功すると十二指腸潰瘍が再発する確率は非常に低くなると言われています。
ピロリ菌陰性で痛み止めを飲んでいる場合には、痛み止めの中止・変更を検討しなければならないケースがほとんど。同時に胃酸を抑える薬を併用し、症状の改善を目指さなければなりません。
傷が小さければ、胃酸を抑える薬を数週間飲み続けることで、傷が治癒する場合が多いです。一方で傷が大きい場合は、内視鏡による治療を行い、穴があいている場合には手術を行うこともあります。
外科の基本情報・知識
外科のブログ情報
以下の都道府県をクリックして外科を検索してください。
「外科」から病院名を入力して探す
外科の関連情報・生活便利情報
関連情報リンク集
病院・医院に関連する省庁サイトです。
法律や制度の確認、統計データの取得など、情報収集にご利用ください。
外科 関連学会一覧
- 日本癌学会
- 日本外科学会
- 日本整形外科学会
- 日本口腔科学会
- 日本気管食道科学会
- 日本胸部外科学会
- 日本脳神経外科学会
- 日本輸血・細胞治療学会
- 日本形成外科学会
- 日本小児外科学会
- 日本脈管学会
- 日本人工臓器学会
- 日本消化器外科学会
- 日本癌治療学会
- 日本移植学会
- 日本心臓血管外科学会
- 日本リンパ腫学会
- 日本大腸肛門病学会
- 日本呼吸器外科学会
- 日本脳卒中学会
- 日本内視鏡外科学会
- 日本乳癌学会
- 日本血栓止血学会
- 日本血管外科学会
- 日本臨床腫瘍学会
- 日本呼吸器内視鏡学会
- 日本手外科学会
- 日本脊椎脊髄病学会
- 日本臨床スポーツ医学会
- 日本熱傷学会
- 日本肺癌学会
- 日本胃癌学会
- 日本造血・免疫細胞療法学会
- 日本脳神経血管内治療学会
- 日本骨粗鬆症学会
- 日本内分泌外科学会
- 日本骨代謝学会
- 日本肝胆膵外科学会
- 日本食道学会
- 公益社団法人 日本口腔外科学会
- 一般社団法人 日本口腔衛生学会
- 公益社団法人 日本口腔インプラント学会
- 一般社団法人 日本顎関節学会
- 特定非営利活動法人 日本臨床口腔病理学会
- 一般社団法人 日本口腔感染症学会
- 特定非営利活動法人 日本臨床歯周病学会
- 一般社団法人 日本歯科審美学会
- 日本顎口腔機能学会
- 特定非営利活動法人 日本顎変形症学会
- 一般社団法人 日本顎顔面補綴学会
- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会
- 一般社団法人 日本小児口腔外科学会
- 公益社団法人 日本顎顔面インプラント学会
- 一般社団法人 日本外傷歯学会
- 一般社団法人 日本口腔診断学会
- 一般社団法人 日本口腔腫瘍学会
- 一般社団法人 日本口腔リハビリテーション学会
- 一般社団法人 日本口腔顔面痛学会
- 一般社団法人 日本口腔検査学会
- 一般社団法人 日本口腔内科学会
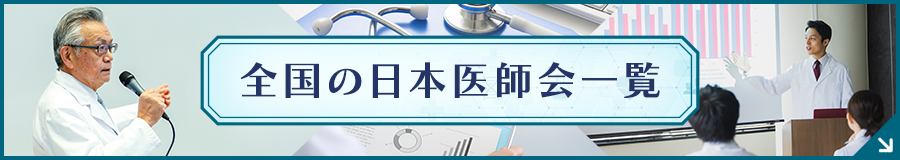
介します。

投稿をお待ちしております。
ホームメイト・リサーチに
口コミ/写真/動画を投稿しよう!
「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。
Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん
- ゲストさんの投稿数
-
今月の投稿数 ―施設
- 累計投稿数
-
詳細情報
―件
口コミ
―件
写真
―枚
動画
―本