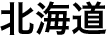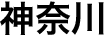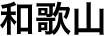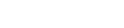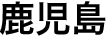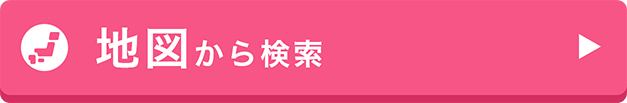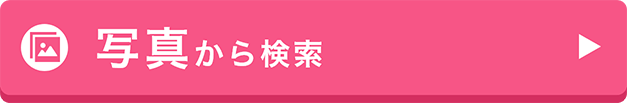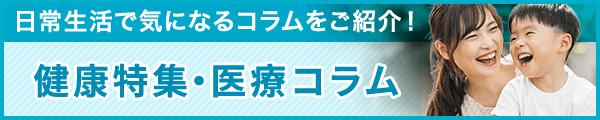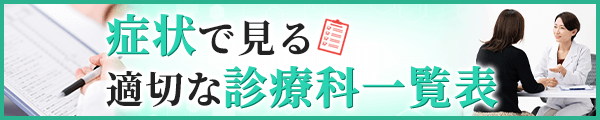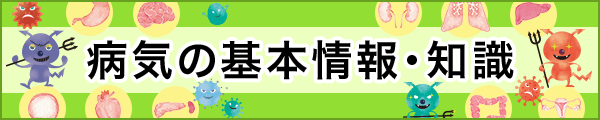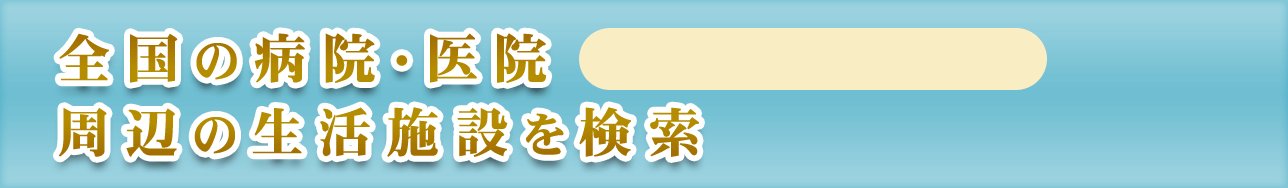 皮膚科
皮膚科
皮膚科病院をお探しの方は、ドクターマップにお任せください!施設情報サイト「ドクターマップ」では、日本全国の皮膚科に対応した病院の情報をまとめました。検索方法もカンタン!都道府県名から地域を選んで、お目当ての皮膚科のある病院が見つかります!
皮膚科とは
皮膚科とは、皮膚の病気を診断し治療する医療分野。皮膚は人間の身体の外側を覆う最大の器官で、体温を調整したり、汗として老廃物を排出したりする作用も持っています。皮膚科はこの皮膚の障害や疾患の治療を通じて、健康な生活の維持に寄与する診療科目です。
皮膚科で治療対象となる主な疾患は、アトピー性皮膚炎や湿疹(しっしん)、ニキビ、白斑(はくはん)、蕁麻疹(じんましん)など。例えば湿疹は皮膚の炎症で赤みやかゆみが生じますが、原因となるアレルゲンを特定して回避しつつ、ステロイド外用薬で治療します。
なお、皮膚科医は、肉眼や皮膚科用の顕微鏡で丁寧な診察を行い、必要に応じて皮膚の一部を切り取って行う検査も実施。治療法も外用薬から光線治療、手術療法と幅広く、患者の状態に合わせて選択されます。
目次
皮膚科で受けられる診療
「皮膚科」は、皮膚に関する疾患を専門的に扱います。口の中などでも目に見える範囲は、ほぼ皮膚科の領域です。また、爪や髪の毛に関する疾患などの治療も行います。
皮膚科で診療される症状は、湿疹、かぶれ、とびひ、いぼ、ニキビ、やけど、アトピー性皮膚炎、脱毛症、皮膚腫瘍、治りにくい水虫、爪の変形を伴う爪白癬、頭部白癬、再発性のカンジダ症、感染症(帯状疱疹・麻疹など)、培養真皮移植など。薬物療法(外用薬・内服など)や外科的な治療で処置します。
皮膚科で診療できる病気一覧
皮膚科で診療できる主な病気をご紹介します。
あせも(汗疹:かんしん)
特徴
あせもとは、汗が原因でなる病気のことで、通常の汗の量より多く量が出る、高温多湿の時期に多く見られます。汗腺が汚れで詰まったり、汗の出口がふさがれたりして皮膚に炎症が起きることが原因です。
あせもには①「紅色汗疹」②「水晶様汗疹」③「深在性汗疹」の3つの種類がありますが、日本では「紅色汗疹」であることがほとんど。熱帯地方で多く見られる「深在性汗疹」は、日本においてはレアケースとなります。
あせもは、乳幼児に多く見られますが、乳幼児も大人と同じ数だけの汗腺を持っていて、小さな汗腺が密集し、汗をかきやすいことから起こるためです。
症状
あせもの症状は、皮膚が腫れてかゆみを伴ったあと、水ぶくれを起こし、赤い発疹ができます。ひどい場合は、かゆみによる不眠や、食欲不振などを引き起こすこともある病気です。
3種類の中で一番症状が軽いものは、②「水晶様汗疹」で、透明あるいは白い水泡が出て、痛みはなく自然に消えることがほとんど。一番症状が重いのは、③「深在性汗疹」で、皮膚の深部で大きくて平らな形状の湿疹が現れます。
あせもが出る場所は、汗腺が多い頭や首、汗が乾きにくいひじの内側、ひざの裏側、お腹、股の部分などです。
治療法
あせもには、ケアが必要です。こまめに汗を拭きとったり汗をかかないように、温度や湿度の調節をしたりと、あらかじめケアをすることで症状の悪化を防ぐことができます。あせもでかゆいからと言って、かいてはいけません。ステロイド系の外用剤を塗り、早めに治しましょう。
かきむしると皮膚の炎症を悪化させ、そこから細菌に感染することもあります。あせもをかくなどして水泡がつぶれると、周辺の部位に感染しかねません。そうならないためにも、つねに清潔にしておくことが大切です。爪を短く切る、汗はこまめに拭くなど、すぐにできることから始めることをおすすめします。
外陰炎(がいいんえん)
特徴
外陰炎とは、腟の入り口周囲にあたる外陰部が炎症を起こす病気です。黄色ブドウ球菌などの細菌や、ヘルペスやヒトパピローマウイルスなどのウイルス、カンジダなどのカビやダニの感染が原因となることがあり、性交渉で感染することも少なくありません。
また、外陰炎は抵抗力の弱い小児や妊婦、エストロゲンの低下した老婦人及び糖尿病患者などでも発症します。下着がこすれたり、刺激の強い洗浄剤で洗ったりすることで炎症を起こすこともあり、腟炎を合併することもしばしばです。
症状
症状としては外陰部全体が赤く腫れたり、強いかゆみやヒリヒリとした痛みを伴ったりします。性器ヘルペスでは外陰部に水疱ができて強い痛みを伴い、重症化すると排尿や歩行が困難になることも。尖圭コンジローマでは、外陰部に乳頭状の腫瘍を認めます。
バルトリン腺炎は、バルトリン腺の排出管が閉塞し、分泌物がたまって細菌が感染し増殖。外陰部にしこりができ、痛みを伴います。毛ジラミが寄生することによる毛ジラミ症では、下着に黒色の点状のシミが付着することも。ダニやカンジダでは、強いかゆみを伴います。
治療法
原因に応じて治療を行います。感染症の場合の治療法は、病原菌に対する薬の投与や塗布です。おりものにも異常がある場合は、同時に腟炎の治療もしなければいけません。原因によって治療方法が変わるため、自己判断で市販楽を使わないようにしましょう。
余計に悪化させてしまい、治療が長引くことがあります。予防としてはデリケートゾーンをとにかく清潔に保つこと。通気性の良い綿下着や服を着用したり、ナプキンやシートをこまめに変えたりすることが大切です。
疥癬(かいせん)
特徴
疥癬とは、ヒゼンダニという小さな虫が人の皮膚に寄生して起こる病気です。人や寝具などから感染し、通常、症状が出るまでの潜伏期間は1~2ヵ月とゆっくり進行。
一方、感染している人と接触し、潜伏期間が4~5日間と短く、急激に症状が現れるものは角化型疥癬と呼ばれます。短い時間であっても人から人に感染し、媒介となりうる感染症のため、病院や施設などで集団生活をする上では、感染している人との接触は特に注意が必要です。
症状
疥癬の症状は腹部、脇、太ももなど、身体のやわらかい部分に赤い湿疹のようなものができ、かゆみが生じます。かゆみは激しく、眠れなくなるほどです。男性の外陰部に感染した場合、数ミリほどの結節ができます。
角化型疥癬の場合は灰色から黄白色の角質がはがれ、それが積み重なってアカのようなものが発生。症状は全身に出ることもあり、痛みはある場合と全くない場合があります。周囲に感染させる場合があるので、同居の人が疥癬と診断されたら早めに皮膚科を受診しましょう。
治療法
疥癬の治療法として、まず原因となるヒゼンダニを殺すことが大切。ヒゼンダニに効く飲み薬や塗り薬を医師に処方してもらいます。塗り薬は、症状が出ていない箇所もダニが媒介しないよう、全身に塗る方が効果的です。
かゆみが伴う場合は、抗ヒスタミン薬の飲み薬を併用します。特に手や指の間、足や外陰部には念入りに塗布しましょう。
治療法は、角化型疥癬と通疥癬では方法が異なるため注意が必要。また、周りに感染しないよう、日常生活も気を付けましょう。入浴は毎日行い、衣類など肌に触れる物は50℃以上のお湯に10分以上浸してから洗濯します。
ガングリオン(がんぐりおん)
特徴
ガングリオンとは、手や足などの関節周辺にできやすい腫瘤のこと。比較的若年層の女性に多く見られる傾向にありますが、どなたにでも発生するのが特徴です。
手の甲や手のひらの指の付け根などにできやすく、腫瘤の硬さや大きさなども人によって異なります。悪性の腫瘍である癌とは違い、良性の腫瘤なので浸潤や転移の心配はありません。
また、痛みもなく、腫瘤ができているだけであれば放置していても差し支えないことも特徴のひとつ。手を良く使うかどうかにかかわらず発生することがあります。
症状
ガングリオンは、米粒くらいのものからピンポン玉くらいのものまで大きさは様々。袋の中はゼリー状の液体で、痛みを伴わないことがほとんどですが、違和感があったり、関節を圧迫したり、近くの神経を圧迫することで痛みやしびれを出すことがあります。
中は液状のため、大きくなったり小さいままだったり、気付かないことも。発生場所は手指や手首が多いことが知られていますが、関節を包む袋や腱を包む鞘など、体中の関節の周りにできる腫瘤です。
治療法
ガングリオンは、腫瘤のみで痛みがなければ治療を必要とするものではありません。しかし、強い痛みが生じるもの、だんだんと大きくなっていくもの、神経が圧迫される症状のある場合は治療が必要となるので、受診しましょう。
治療はガングリオンに直接注射針を刺し、中のものを取ってもらう方法や、腫瘤を押しつぶして袋を破いて内容物を出す方法などです。再発を繰り返す場合や、神経圧迫による神経麻痺がある場合には、手術により摘出することもあります。
化粧品皮膚炎(けしょうひんひふえん)
特徴
化粧品皮膚炎とは、化粧品など直接肌に触れるものによって起きる皮膚炎のこと。社会人になりたての化粧をしはじめて間もない人や、長年化粧品を使っている人が発症することもあります。
化粧品皮膚炎の原因は、化粧品を作るときに必要な薬品(界面活性剤)が含まれている化粧品に反応し、発症することが主です。ただ、症状が軽いため重大なことを見逃してしまうこともあるため注意しましょう。
化粧品皮膚炎を抱えたまま、長期に亘り化粧品を使用していると症状が悪化し、蓄積して障害を引き起こすことになるため注意が必要です。
症状
化粧品皮膚炎の症状は、手や頭、顔、首など化粧品を使う箇所にできます。化粧品を使ったあとに顔がつっぱるなどの症状や、皮膚が赤みを帯びたり、赤いボツボツが現れたりする点が特徴です。
しばらく放っておくと色素沈着を起こしてしまい、綺麗にもとに戻すのは容易ではありません。ひどい場合は、かぶれが生じることもあります。
また、化粧品を変えるとすぐに症状が出る人もいますが、同じ化粧品を使い続けているうちにだんだんと気付くという人もいて出方は様々です。
治療法
化粧品皮膚炎は、基本的にはステロイド軟膏を塗ることで対処していきますが、かゆみや痛みがひどい場合は、抗ヒスタミン剤やステロイド薬を投薬する場合もあります。症状が出た場合は、ただちに化粧品を使うことをやめましょう。
通常は、原因となる化粧品をやめることで症状は治まりますが、複数の原因が関係していることも少なくありません。その場合、一般的な防腐剤や香料が原因となっていることが多く、アレルギーによる皮膚炎となるため判断には注意が必要です。
紅皮症(こうひしょう)
特徴
紅皮症とは特定の疾患ではなく、原因となる疾患の影響で、全身の皮膚の90%以上が変色、あるいは変形した状態を指すものです。
原因疾患には、腫瘍性の白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫の腫瘍性疾患と、アトピー性を含む各種皮膚炎、疥癬、天疱瘡などの非腫瘍性疾患があります。特に、アトピー性皮膚炎から紅皮症への移行が多い他、抗生物質の服用後に発症する紅皮症もありますが、この場合には薬剤服用を中止せざるを得ません。
症状
紅皮症は初期には皮膚が赤くなり、慢性化すると黒色に変色するという、皮膚の色の異常が症状の特徴です。また、皮膚が剥がれ落ち、皮膚が硬く魚のうろこ状に変わり、それが剥がれ落ちることもあります。
皮膚症状には、強いかゆみも特徴的で、皮膚の炎症が起こったあとに起こる血管拡張のせいで、発熱、脱水、浮腫などが起こることも少なくありません。また、皮膚の再生が起こらずに消失が進むため、皮膚の主成分であるタンパク質からできているケラチンが失われていき、このタンパク質の消失による栄養不良に陥るという問題もあります。
治療法
紅皮症では、まず、原因疾患の見極めと、その対応が必要です。かゆみ止めなどの対症療法としては、外用と内服の抗ヒスタミン薬やステロイド薬、高濃度ビタミンD3外用薬が有効。ただし皮膚表面が障害されていて薬に対して過剰に反応する可能性があるため、一部の患者では外用薬の使用を避けなくてはいけません。
その他、光反応性の薬剤と長波長紫外線照射するPUVA法、ナローバンド紫外線治療、ビタミンA 誘導体内服、免疫抑制剤内服などが原因疾患ごとに行われます。
主婦湿疹(しゅふしっしん)
特徴
主婦湿疹とは、日常的に水仕事をしている主婦に多く見られる手荒れや湿疹のことです。しかし、主婦だけに限らずとも手洗いを頻繁にする人にできやすく、調理師や清掃業者の方にも見受けられます。
症状は個人差がありますが、手のひらや指の関節が乾燥してぱっくり割れてしまったり、強いかゆみを感じたり、水疱ができてしまう症状のことを言います。また、冬場に起こりやすいあかぎれとは異なり、夏場にも発症する可能性があるのが特徴です。
似たような症状の病気である「手白癬」や「掌蹠膿疱症」と勘違いをされるケースもあります。
症状
主婦湿疹の症状は、乾燥型と浸潤型に分けられます。
指から手全体が赤く腫れたり、固くなったり、指先のひび割れや指紋が消えるなどの症状の人は乾燥型で、季節的には秋冬に症状が出るタイプです。
浸潤型は手指、手のひら、手の甲など広範囲に亘り、赤く腫れポツポツの水泡ができ、かゆみを伴うタイプ。季節的には春夏に多く見られます。浸潤型は痛みやかゆみを伴うので、症状が悪化しやすいのが特徴です。化膿を引き起こすこともありますから、早めに受診しましょう。
治療法
主婦湿疹は治療法としては、日常的なケアが大切です。まずは原因の物質となるものを除去しましょう。
洗剤を使うときにはゴム手袋を使用しても大丈夫ですが、ゴムにより悪化させることもあるため、ゴム手袋の下に綿の手袋をすると良いでしょう。また、洗剤やシャンプーを刺激の弱い物に変える、触れる回数を少なくするなどして、刺激物を避けることも大切です。
もちろん、保湿剤の使用で改善されることもあります。市販の保湿剤で改善されない場合は、早めの受診がおすすめです。
脂肪腫(しぼうしゅ)
特徴
脂肪腫とは、皮下に発生する脂肪細胞の塊からなる良性の腫瘍です。皮膚の浅い部分から筋肉層まで色々な部分に発生し、1個しかできない場合から、複数個できる場合まで色々あります。
年代を問わず発症しますが、特に40~50代の女性に多く、背中、肩、頸部、大腿部にできやすく、大きさも多様です。
一般的には皮膚への継続体な刺激と関係があることや、腫瘍組織の中に染色体異常が見つかったという報告もありますが、脂肪腫のはっきりとした発生原因はまだ分かっていません。
症状
脂肪腫は、皮膚がドーム状に盛り上がるため、外見上の問題があるものの、痛みなどの特別な症状は出ないことが多いです。類似の様相を示す他の病気であるガングリオンとの違いは、脂肪腫の方がやわらかくて、ガングリオンのように手の関節付近などにはできません。
また、アテロームとの違いは、目で見たときの色味が、脂肪腫でははっきりとしないのに対して、アテロームは黒っぽく見えます。また腫瘍サイズがどんどん大きくなることがあるのも脂肪腫の特徴です。
治療法
脂肪腫は放置しておいても特に問題はありませんが、大きくなって人目が気になる場合や、可動性が障害されるような場合には手術も可能です。
脂肪腫は液体でできている訳ではないため、外からの吸引によって排除することはできません。手術により摘出してしまえば、再発の心配は無視できます。
ただ、ごく稀に悪性の脂肪肉腫の場合があるため、腫瘍のサイズが大きい場合や、短期間に大きくなった場合には画像検査を行いましょう。
帯状疱疹(たいじょうほうしん)
特徴
帯状疱疹とは、身体の抵抗力が低下しているときに水痘・帯状疱疹ウイルスが神経を通って皮膚に感染する病気のこと。子供のころに水疱瘡にかかったことが原因で、ウイルスが体内に残ります。
普段は体内に潜伏していますが、疲れやストレス、加齢などによる体力の低下をきっかけに潜伏していたウイルスが活性化。神経を伝わって皮膚に出てきて、水ぶくれとなるのが帯状疱疹です。多くは50歳以上に見られますが、何歳でも発症の可能性があるため注意しましょう。
症状
顔・胸・腹・上下肢などの知覚神経に、小さな水ぶくれが身体の左右のどちらかに帯状に現れるのが特徴。始めは虫刺されと同じような紅斑のある水痘が現れ、またかゆみを伴うため、蚊に刺されたと勘違いすることも少なくありません。
水ぶくれは4週間程度で消えますが、ちくちくとした強い痛みがあり、発症後にも痛みだけが残ることがあります。この症状は帯状疱疹後神経痛と呼ばれ、人によっては何年も続くことがあるため早期の治療が必要です。
治療法
帯状疱疹ではウイルスと痛みに対して治療が行われます。ウイルスに対しては、抗ヘルペスウイルス薬を飲み薬で摂取することで、繁殖を抑え水ぶくれの広がりや痛みを軽減。また、発症してから2~3週間までのちくちくとした痛みには、非ステロイド系消炎鎮痛薬を使用します。
いずれも薬の効果が出るまでに数日かかることがあるので、即効性がないからと言って自己判断で薬をやめたり、増やしたりしてはいけません。医師の指示に従いましょう。
また、帯状疱疹は体力の低下も一因となるため、湯船につかり身体を温める、十分に睡眠を取って身体を休めるなどの養生も大切です。
多発性筋炎(たはつせいきんえん)
特徴
多発性筋炎とは、国の指定難病で自己免疫性疾患のひとつです。身体の自己免疫に異常をきたし、自分の身体を異物と勘違いしてしまうことで細胞を攻撃してしまいます。
病気に遺伝性はありませんが、自己免疫の異常は遺伝することがあり、近親者に同じ病気が現れる場合も珍しくありません。腕や足の筋肉に出るため生活に支障があり、さらには筋肉の炎症だけでなく関節や心臓、肺など内蔵に障害が出ます。
性別や年齢に関係なく発症。比較的女性に発症することが多く、40~50歳代の中年層に見られますが、詳しい原因については、いまだ不明です。また症状は、小児のほうが急激に現れます。
症状
多発性筋炎の主な症状を紹介します。
筋肉の障害
筋肉の炎症により疲れやすくなったり、力が入らなくなったりします。太ももや二の腕、首の筋肉に起きやすい状態です。
緩やかに発症するため、気付かない場合もありますが、病気が進行すると、寝返りや起き上がり動作、歩行、階段の昇降などが困難になります。
関節症状
関節の痛みを感じることがありますが、軽症の場合が多いようです。
レイノー現象
寒い日に指が白くなったり、紫色に変色したりするレイノー現象が見られることもあります。
呼吸器症状
咳や息切れ、呼吸困難などを引き起こす間質性肺炎を発症するケースもあります。
心臓の症状
心臓の筋肉が障害を起こし、心不全や不整脈を起こす場合があります。
全身症状
発熱や倦怠感、食欲不振、体重の減少などが見られることがあります。
治療法
多発性筋炎の治療法には薬物療法が用いられ、主に「副腎皮質ステロイドホルモン」の使用が必要です。病気の症状の進行具合にもよりますが、患者の体重の0.5mgから1.0mgのステロイドを投与し、筋肉の炎症や筋力に回復が見られるかどうか観察、効果が見られてからリハビリテーションなどを行います。
効果が見られない場合やステロイドによる副作用がある場合には免疫抑制剤を併用し、肺病変や悪性腫瘍などがある場合には、その治療を最優先しましょう。
白皮症(はくひしょう)
特徴
白皮症とは、メラニン色素合成遺伝子の変異によって全身の皮膚が白くなるだけでなく、肺炎にかかりやすいなどの他の病気も合併する場合がある、難病指定164号に認定されている、遺伝性の皮膚疾患です。
目にも症状が出るため、別名、眼皮膚白皮症。近親婚の場合の子供が発症しやすく、遺伝子変異の種類による分類が行われ、メラニン合成が全く起こらないOCA1型から、あまり症状の出ないOCA7型、及び合併症を持つ型に区分されます。
症状
症状の最大の特徴は、全身の皮膚の色が白い点。その他には、頭髪が白や銀色で薄く、目の症状として、ピント調節機能障害、眼振の発生、光への感受性が高まるなどの症状です。
日本人に最も多いメラニン合成が全く起こらないOCA1型では、生涯を通じて皮膚の色は白いままで推移。日光に対する防御を行っても、年齢とともに、メラノーマを含む皮膚癌の発生を抑えることができません。
合併症を伴う型の症状は、出血傾向とともに、間質性肺炎、肉芽腫性大腸炎、免疫不全などを発症します。
治療法
白皮症の根本的な治療薬は、いまだ見つかっていません。したがって、現在のところは日光に対する防御を中心とした対応が取られています。
すなわち、皮膚癌の発症リスクを下げるために、紫外線防御用のサンスクリーン(SPF30以上)を皮膚に塗る他、屋外に出るときは色の濃い服装や帽子を着用し、日中屋外での活動をできるだけ控えるなどして、皮膚の日光暴露に注意が必要です。それとともに、皮膚癌の定期的な検診も必須。目の障害に対する対応としては、矯正メガネやサングラスの使用、眼振の外科治療などが行われます。
リール黒皮症(りーるこくひしょう)
特徴
リール黒皮症とは、皮膚が黒褐色に色素沈着してしまう病気のことで、化粧品などが原因で発症することがほとんど。原因不明のこともありますが、素因があった人が化粧品などによる炎症を起こし、表皮の基底部が破壊され、本来は基底部にあるはずのメラニン色素が真皮内に入り込んでしまうためです。
原因物質にタール色素(赤色219号)、ズダンⅠ、パラベンなどが報告されています。現在、あらゆる化粧品メーカーの商品から、これらの物質が除外されるようになり、リール黒皮症は激減しました。また、ナイロン製のタオルなどでこすりすぎることも原因のひとつです。
症状
リール黒皮症の症状として、初めは顔や首筋がなんとなくかゆい、赤みがかっているように感じることが多いです。そしておおよそ半月程度たって頬や額、瞼などの位置を中心に黒褐色の色素沈着が起こります。
それらはまだらで、それぞれの境界がはっきり見えません。首などに症状が出ることもありますが、化粧品を使用する部位に出ることが大半。色素沈着が始まったあともかゆみが残ることも少なくありません。顔面に起こりやすい症状なので、他者に指摘されることもあります。
治療法
リール黒皮症を完治する治療は現在確立されていません。そのため、症状が出ないように、悪化しないように対処することが優先。リール黒皮症と診断されたら、まずは日常生活を見直し、原因物質を取り除くことが必要です。
早期発見できた場合は、原因物質の除去のみで軽減することもあり、かゆみがあるときは、ステロイド剤の軟膏や抗ヒスタミン系の内服で症状を抑えます。
原因物質による影響が取れれば色素沈着は消えますが、再発しないように注意しなければなりません。日焼けやマッサージなどの刺激を避け、化粧品や洗顔石鹸も刺激の少ない物を使いましょう。
皮膚科の基本情報・知識
皮膚科のブログ情報
以下の都道府県をクリックして皮膚科を検索してください。
「皮膚科」から病院名を入力して探す
皮膚科の関連情報・生活便利情報
関連情報リンク集
病院・医院に関連する省庁サイトです。
法律や制度の確認、統計データの取得など、情報収集にご利用ください。
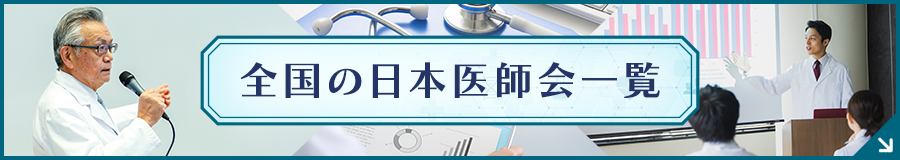
介します。

投稿をお待ちしております。
ホームメイト・リサーチに
口コミ/写真/動画を投稿しよう!
「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。
Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん
- ゲストさんの投稿数
-
今月の投稿数 ―施設
- 累計投稿数
-
詳細情報
―件
口コミ
―件
写真
―枚
動画
―本